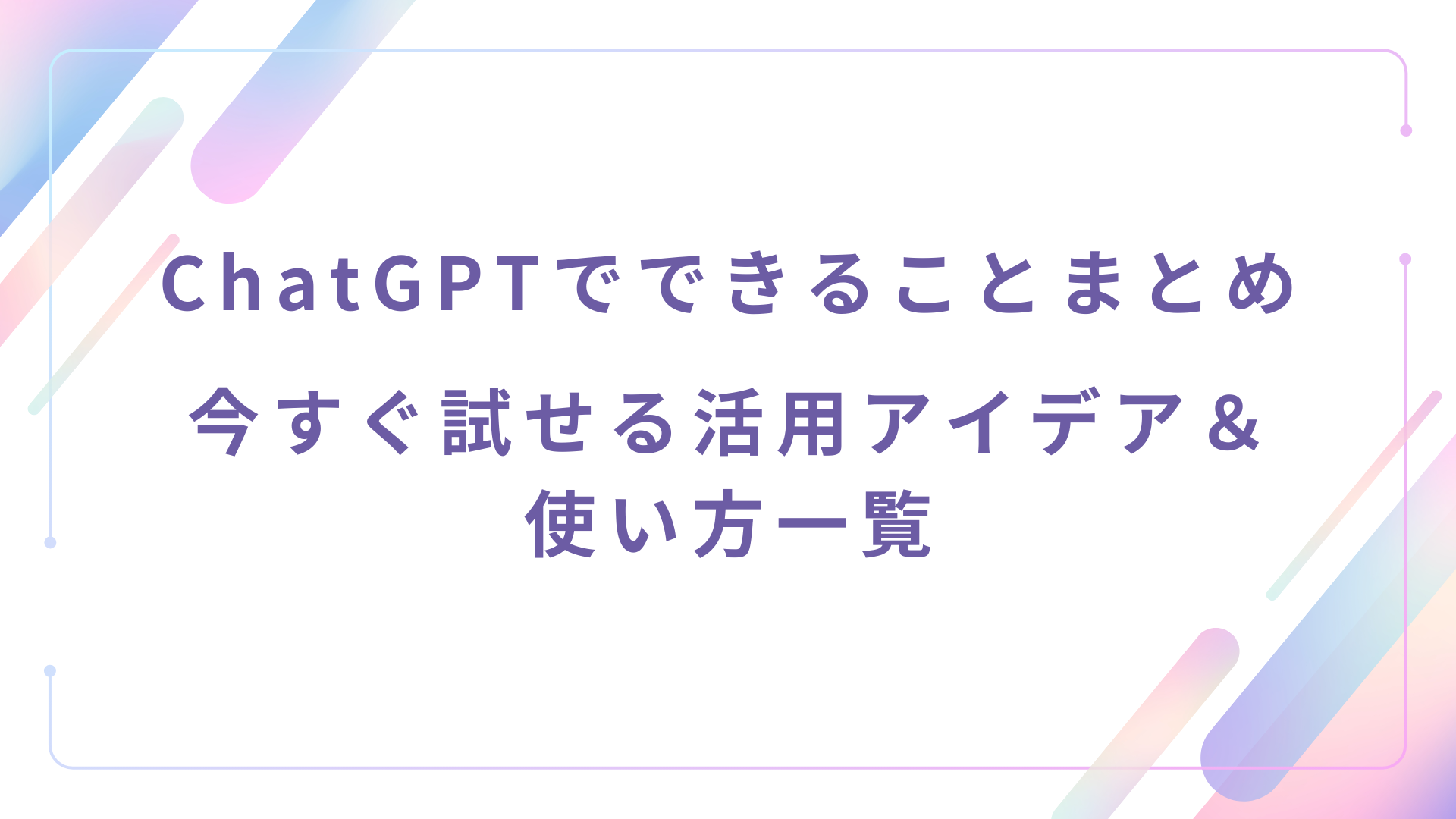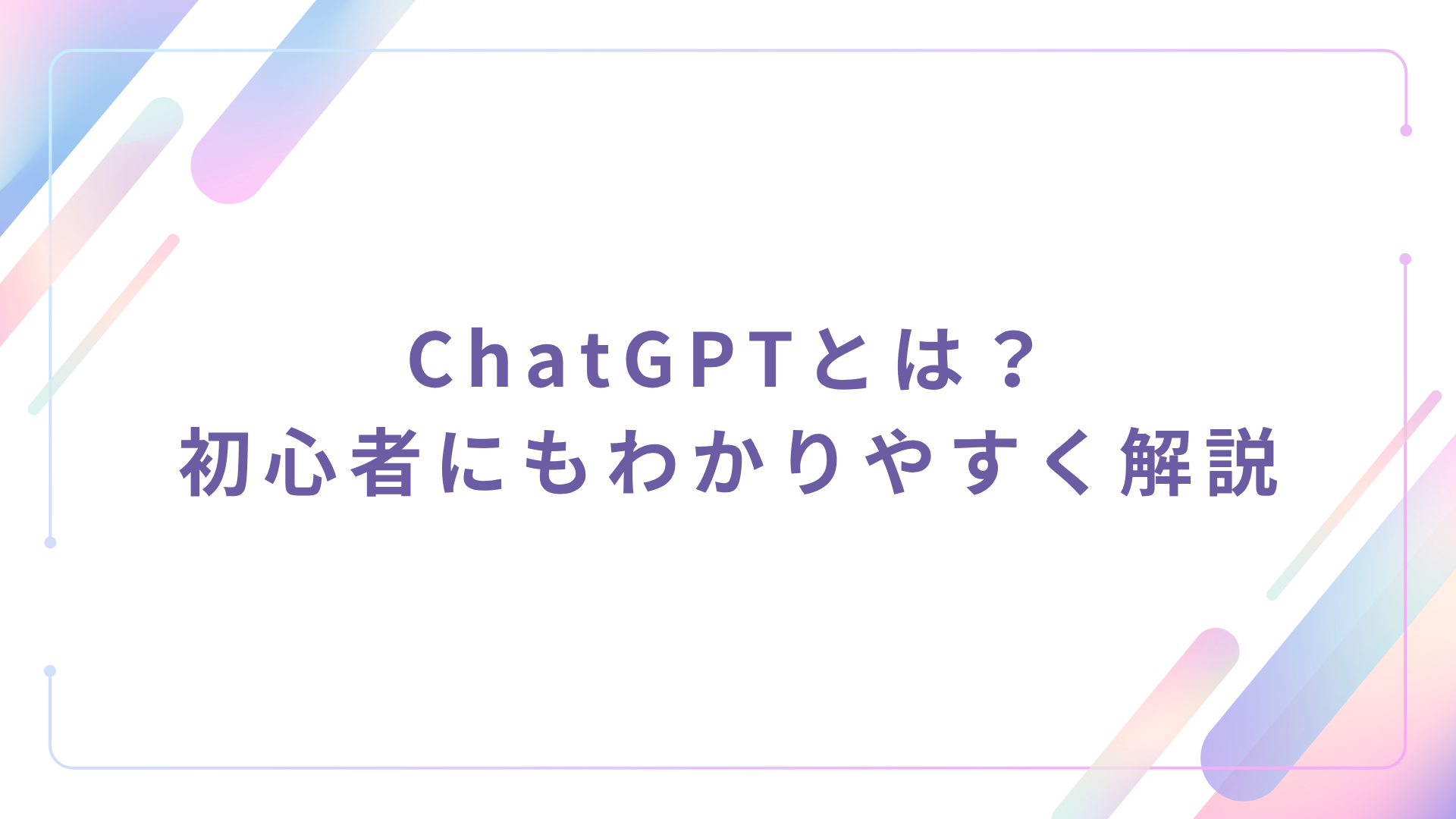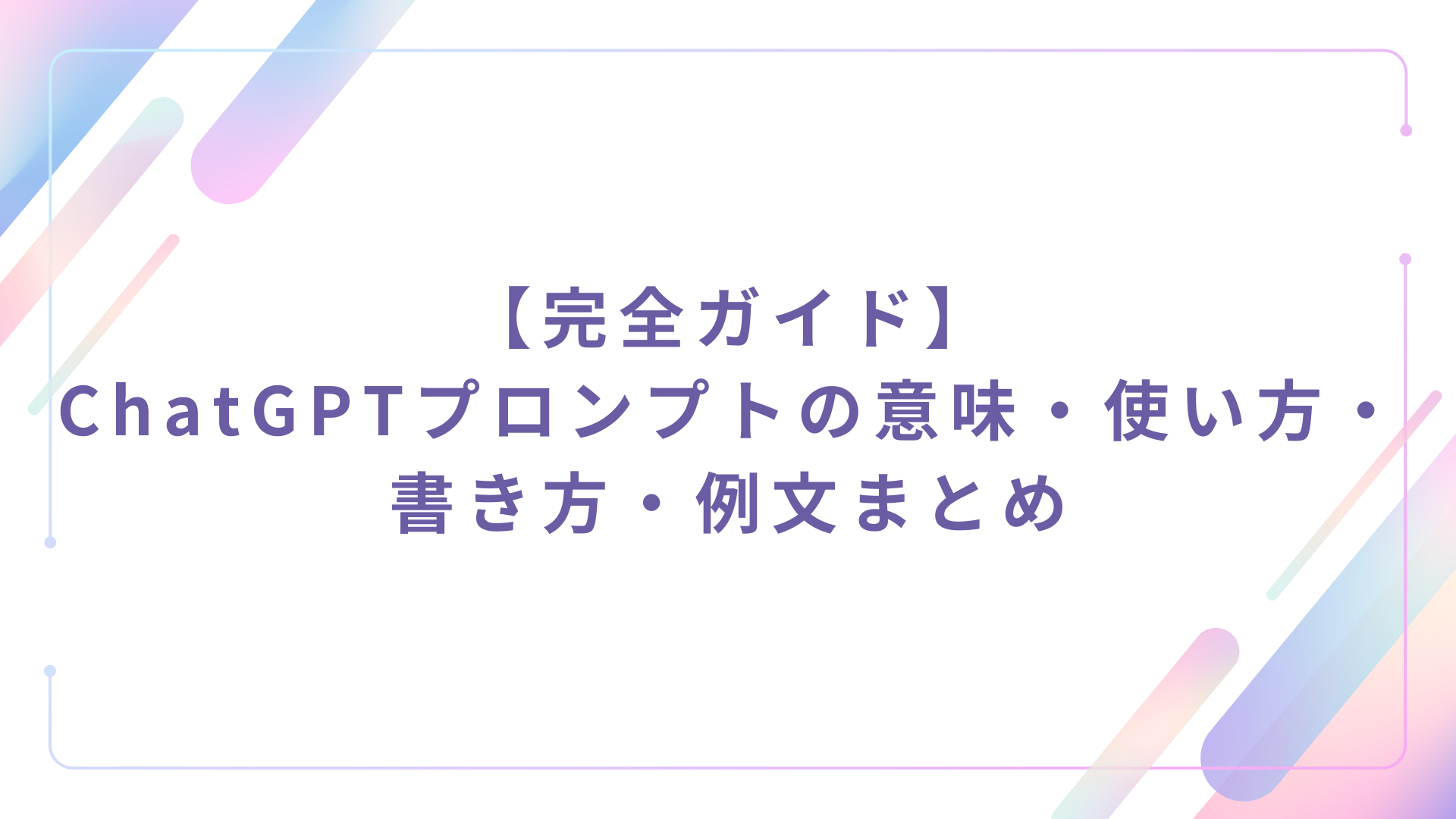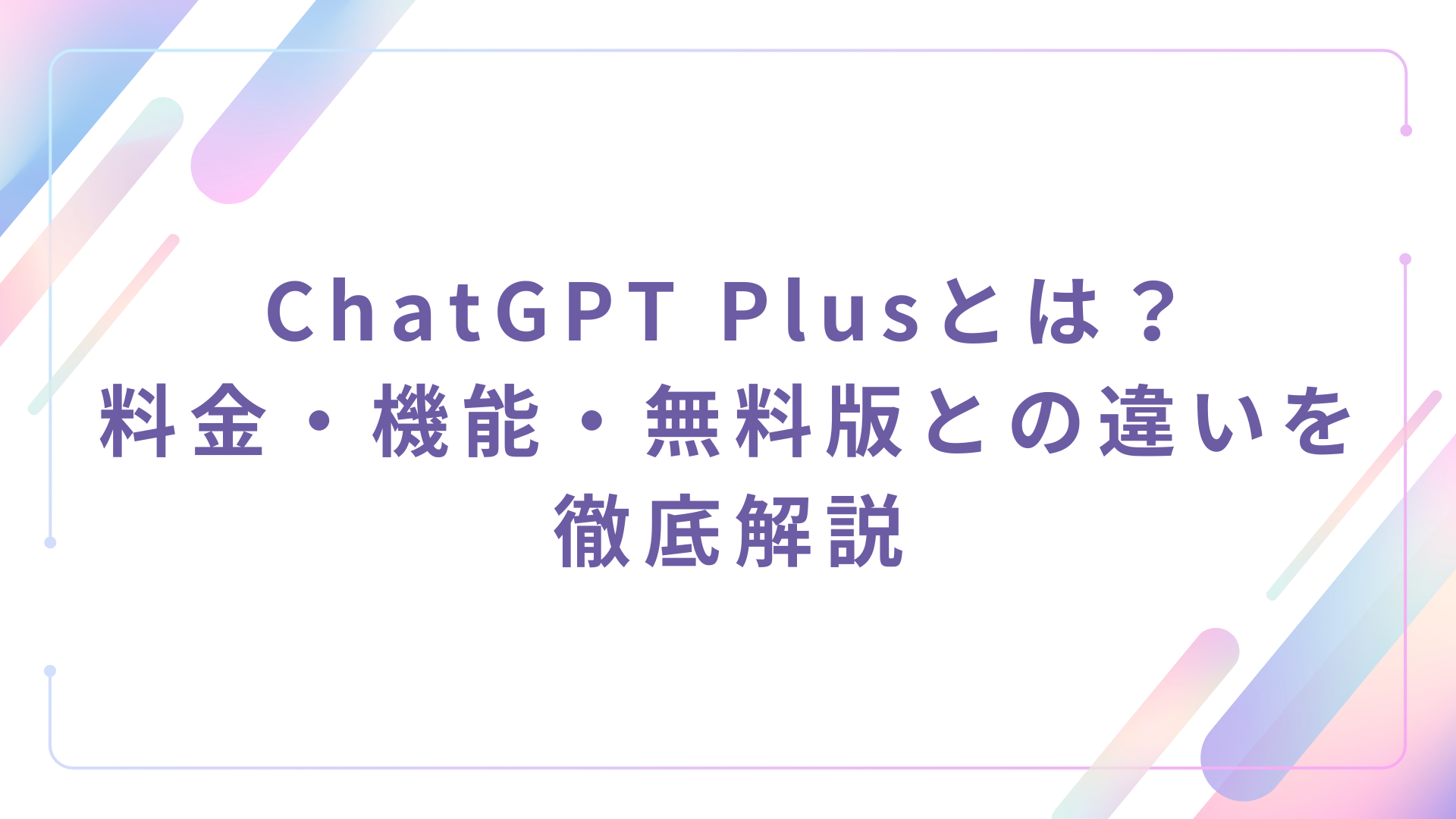AIの「ハルシネーション」とは?ChatGPTでも起こる誤情報の正体と対処法
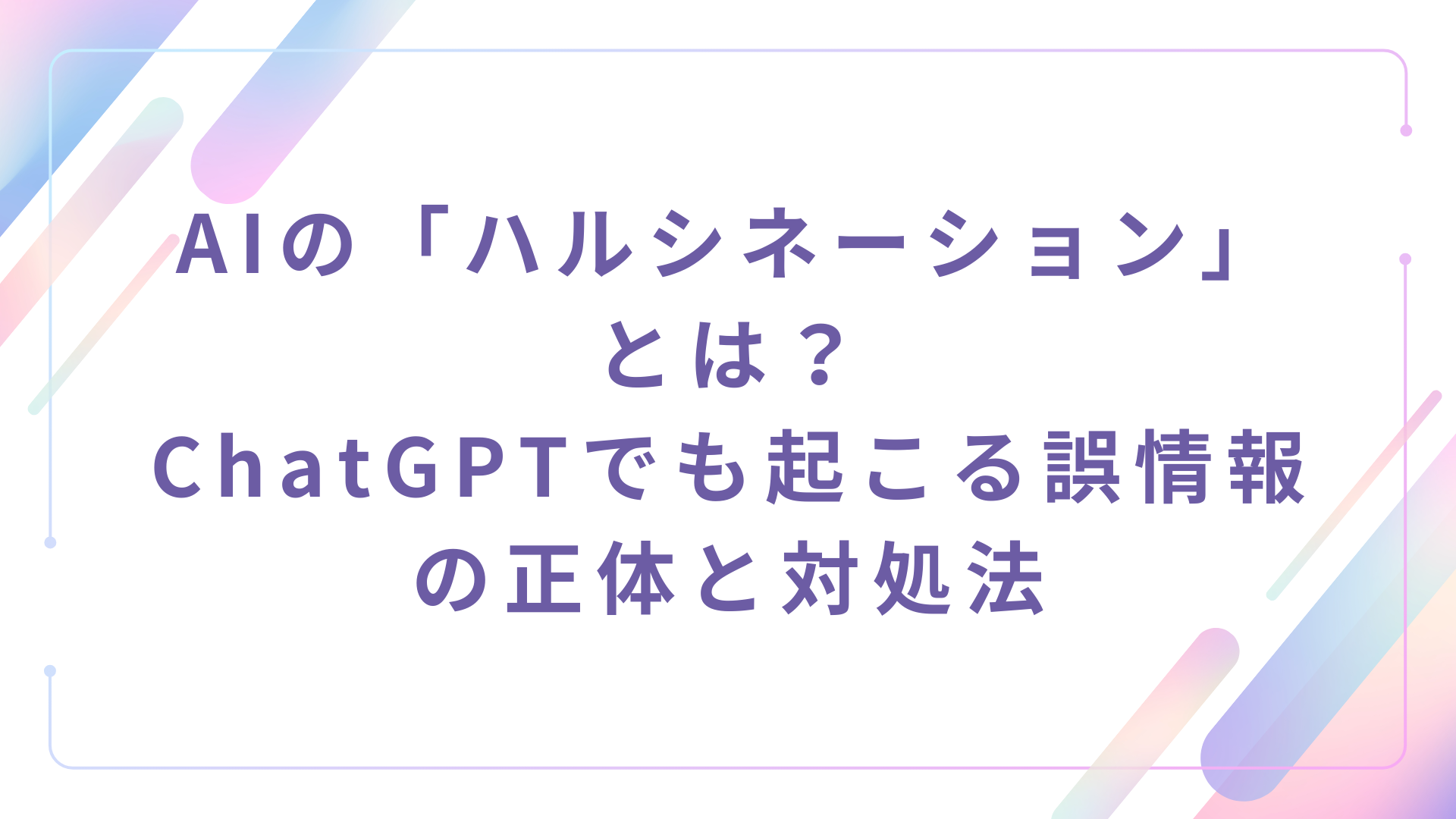
ChatGPTを使っていて「それっぽいけど、なんか違うかも…」と感じたことはありませんか?それは「ハルシネーション」と呼ばれる、AIがもっともらしい誤情報を出力してしまう現象かもしれません。
本記事では、ハルシネーションとは何か、なぜ起きるのか、そしてどのように対処すればいいのかを、ChatGPTを例にしながら解説します。
AIと上手につき合っていくために、ぜひ参考にしてください。
あわせて読みたい:[ChatGPTとは?初心者にもわかりやすく解説|できること・使い方・無料と有料の違いも紹介]
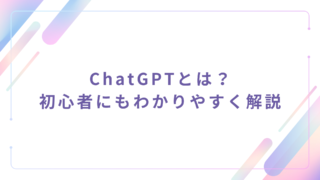
ハルシネーションとは?意味と使われ方
そもそも「ハルシネーション」の語源と本来の意味
「ハルシネーション(hallucination)」はもともと医学や心理学の用語で、幻覚や錯覚を指す言葉です。目の前にないものが見えたり、聞こえたりする現象を指し、人間の知覚の異常を表す際に使われてきました。
AIにおける「ハルシネーション」とは何か
この言葉がAIの世界で使われるようになったのは、主にChatGPTのような大規模言語モデルが登場してからです。AIがあたかも正しそうな文章を生成しながら、実際には事実と異なる内容を提示してしまう現象を「ハルシネーション」と呼びます。
なぜハルシネーションが起きるのか?
AIは情報を「理解している」わけではない
AIは言葉を統計的に処理して文章を組み立てています。人間のように意味を理解しているわけではなく、学習したパターンをもとに最も確率の高い語句を選んで出力しています。そのため、事実確認が必要な場面では誤った情報をもっともらしく出してしまうのです。
文脈や学習データの偏りによる生成のズレ
ChatGPTはインターネット上の膨大なテキストデータを学習していますが、その中には間違った情報も含まれています。また、質問の文脈や単語の使い方によって、微妙にズレた回答が生まれることもあります。
ChatGPTにおけるハルシネーションの具体例
実際に体験したハルシネーション例
私自身もChatGPTを日々使っていて、「あれ?なんかおかしい…」と思う回答に出会うことが何度もありました。ここでは、その中でも印象に残っている“間違った回答(ハルシネーション)”を紹介します。
例①:銘柄コードと企業情報が一致しない【株式投資編】
ChatGPTに株の相談をしていた際、銘柄コードと企業名が一致しないことがありました。
たとえば、「コード××××(企業名)」と提示されたものの、実際に調べるとコードに該当する企業は別会社だったり、株価も全く違うものでした。
このようなことは一度や二度だけではなく、何度か繰り返し経験しています。
その都度「違うのでは?」と指摘してみると、すぐに誤りを認めて訂正してくれる場合もあれば、何度指摘しても同じ間違いを繰り返すこともありました。
例②:「Soraは使えない」と繰り返される【ChatGPT Plus編】
ChatGPT Plusを契約していた私は、動画生成AI「Sora」を使いたくて、ChatGPTに使えるかどうか何度か質問しました。
しかしそのたびに「Soraは一般公開されておらず、Plusでも使えません」という否定的な回答ばかり。
ところが実際にログインしてみると、問題なくSoraが使える状態でした。
このように、現実とは異なる情報をAIが断言してくるのもハルシネーションの一例です。
あわせて読みたい:[ChatGPT Plusとは?料金・機能・無料版との違いを徹底解説]
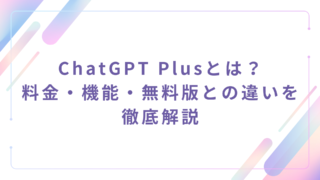
正しい情報と区別がつきにくい理由
ハルシネーションのやっかいな点は、出力された情報がとても自然で信ぴょう性が高く見える点です。一般の検索結果のように裏付けがあるわけではなく、AIの「予測」に過ぎないため、知識のないユーザーほど信じてしまいやすいのです。
なぜAIの間違いを信じてしまうのか?
ChatGPTなどの生成AIが出す答えは、実は「予測」にすぎません。
例えば、Googleなどの検索エンジンでは、実際に存在するニュース記事や公式サイト、論文などが表示され、ユーザーはその出典を確認することができます。
一方、ChatGPTは、過去に学習した膨大なテキストをもとに、「この質問にはこう答えるのが自然だろう」という予測に基づいて文章を生成しています。つまり、特定の資料や根拠を元にしているわけではなく、“もっともらしい答え”を作っているのです。
このような仕組みのため、ChatGPTはときどき実際には存在しない情報や事実と異なる内容を生成してしまうことがあります(これが「ハルシネーション」と呼ばれる現象です)。
知識が少ない人ほど信じてしまうリスク
ChatGPTの回答は、とても自然な文章で返ってくるため、一見すると「正しそう」に見えるのが特徴です。
しかし、その内容が正しいかどうかを見分けるのは、知識や経験がないと難しいこともあります。とくに医療や法律、お金に関するジャンルでは、誤った情報を鵜呑みにすると大きなリスクになる可能性もあります。
ハルシネーションを防ぐ・見抜くためにできること
回答の検証方法・ファクトチェックの重要性
ChatGPTの回答はそのまま鵜呑みにせず、他の情報源(公式サイト、ニュースなど)で確認する習慣をつけましょう。特に数値や固有名詞、日付などは誤りが発生しやすいポイントです。
AIの得意分野・不得意分野を理解すること
文法チェックやアイデア出しなどは得意ですが、時事ニュースや最新の固有名詞、法的解釈などには弱い傾向があります。AIの特徴を理解して使うことで、誤情報への対処がしやすくなります。
ChatGPTが得意なこと・苦手なことをジャンル別に表で整理!
ChatGPTはとても便利なツールですが、すべての分野で完璧というわけではありません。得意なこと・苦手なことには傾向があります。ここではジャンルごとに、ChatGPTの強みと注意点を表でまとめてみました。
| ジャンル | 得意なこと | 苦手・注意が必要なこと |
|---|---|---|
| 情報の要約・整理 | 長文の要約、箇条書き化、ポイントの抽出など | 最新情報・ニュースには弱い |
| 文章作成 | ブログ、メール文、ストーリーなど自然な文章の生成 | 専門分野では誤情報を含むことがある |
| アイデア出し | ブレスト、企画案、ネーミング、キャッチコピーなどの発想系 | ニッチで具体的すぎるテーマには弱い |
| プログラミング | 基本的なコードの生成、エラー修正、解説など | 複雑なアルゴリズムや実行環境によっては動かない場合がある |
| 英語・外国語学習 | 英作文添削、英語での会話練習、単語や文法の説明など | 完全な翻訳や高度な語学的ニュアンスの理解には限界がある |
| 感情的な相談・対話 | 優しく寄り添うような会話、心の整理の補助など | 医療・心理の専門家が必要な悩みには対応できない |
まとめ:ハルシネーションとどう付き合うべきか
ハルシネーションは生成AIの限界によって起こるものであり、注意すべき特性のひとつです。
完全に防ぐことは難しくても、AIの出力に”疑いの目”を持ちつつ活用すれば、十分に便利なツールとして使いこなすことが可能です。正しい使い方を知ることで、ChatGPTの魅力を最大限に活かすことができます。